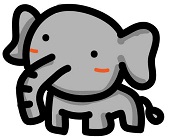お正月と言えば『お餅』、お餅と言えば鏡餅ですよね。
新婚さんであれば、鏡餅も手作りでと気合いを入れる方も多いのではないでしょうか。
しかし、鏡餅は1月11日の鏡開きまでは飾っておくものです。
季節的にも、とてもカビやすいのですが、カビを防止する方法はご存知でしょうか。
そこで今回は、鏡餅の作り方やカビを防止する方法、鏡餅の飾り方と切り方の簡単な方法を紹介していきたいと思います。
鏡餅の作り方でカビを防止するには?正しい飾り方は?

鏡餅の作り方は、お餅を作るだけと思っている人もいるかもしれません。
しかし、単純にお餅を作るだけでは、飾っている間にカビが生えてしまいます。
そこで、鏡餅の作り方でカビを防止する方法と、鏡餅の作り方や飾り方について紹介していきます。
![]() まず意外に思うかもしれませんが、鏡割りのカビ防止の簡単な方法は、アルコール消毒です。
まず意外に思うかもしれませんが、鏡割りのカビ防止の簡単な方法は、アルコール消毒です。
鏡餅の周りをアルコールでコーティングするだけで、カビは大幅に防げます。
アルコールは日本酒や焼酎、ウォッカでも大丈夫ですが、日本酒はお酒臭くなるので、アルコールの臭いが苦手な人は避けたほうがいいと思います。
ウォッカは値もはるのでもったいないので、アルコールは焼酎をオススメします。
次に、鏡餅の作り方と飾り方です。
なぜ12月28日なのかというと、12月28日は「末広がり」の意味があり、縁起がいいとされているからです。
では飾り方ですが、地方によっても異なりますが、基本的には橙(だいだい)、ゆずり葉、うらじろ、半紙があれば大丈夫です。
![]() もちと半紙の間にうらじろと、ゆずり葉を置けば、飾り付けの完成です。
もちと半紙の間にうらじろと、ゆずり葉を置けば、飾り付けの完成です。
このように鏡餅の作り方で、カビを防止するために、焼酎でコーティングをしてみてください。
鏡餅の作り方、飾り方も基本を覚えておけば、とても簡単ですよ。
鏡餅の切り方で簡単の方法とは?

鏡開きは通常、1月11日に行うのが好ましいとされています。
しかし、鏡餅を切るのは重労働ですよね。
鏡餅の切り方で簡単な方法があれば、知りたい人も多いのではないでしょうか。
鏡餅の切り方で、簡単な方法についてまとめていきます。
みなさんは鏡開きを行う際に、鏡餅は何を使って切っていますか?
おそらくは、ほとんどの人が包丁を使っているのではないかと思います。
ですが、実は包丁を使って切る、これは本来してはならないことなのです。
鏡餅は本来切るものではなく、割るもので、刃物を使うことは切腹を連想させてしまうので、かつては厳禁でした。
しかし、トンカチや金槌を使っても固いお餅は、なかなか割ることができないため、現代では包丁で切ることが主流となっています。
そんなウンチクはさておき、さっそく鏡餅の切り方について簡単な方法を2つ紹介します。
電子レンジでラップをかけずに、5分ほど温めてみましょう。
柔らかくなりすぎても切りにくくなってしまうので、様子を見ながら、慎重に加熱するようにしてください。
お餅は中から柔らかくなるので、外側は少し硬いぐらいが切り時になります。
お餅を水に一晩つけておき、その後で電子レンジで加熱します。
水につけておくことで、固くなったお餅の表面を戻すことができるため、電子レンジだけを使うよりも、お餅が美味しくなります。
![]() 鏡餅の切り方で簡単な方法は、「一晩水につけたお餅を電子レンジで加熱する」です。
鏡餅の切り方で簡単な方法は、「一晩水につけたお餅を電子レンジで加熱する」です。
まとめ
鏡餅の作り方において、カビを防止する方法はアルコール消毒がオススメです。
焼酎を使うのが一番経済的ですね。
また、飾り方も基本はとても簡単で、橙、ゆずり葉、うらじろ、半紙があれば完成します。
最後に鏡餅の切り方ですが、鏡餅を切るのが一番大変な作業でしょう。
美味しく頂くための最後の難関です。
簡単は方法は、「一晩水につけたお餅を電子レンジで加熱する」です。
せっかく作る鏡餅、美味しく頂きたいものですね。